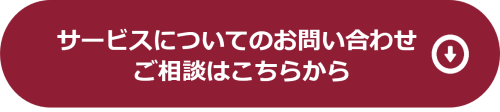組織のこれからを作るための社員研修とは?
組織のこれからを作るための社員研修とは?
社員研修の目的
最初に企業が社員研修を実施する目的を確認します。
ビジネスで必要な知識やスキルの習得と向上
社員研修の目的の1つ目は、新しい技術や業務に関連するスキルの習得、特定の職務に必要な専門知識の強化といったビジネスで必要な知識やスキルの習得向上です。研修受講によってスキルを身に付けるとともに、自分の仕事を振り返り、学んだことをどのように業務に活用するかを考えることで、より高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
スキル・知識の向上は、より高い目標への挑戦や新しいことへのチャレンジも後押しします。このように、社員研修を実施することによるスキル・知識の向上は、社員の能力開発と組織の競争力向上のためも不可欠です。
リーダーシップとマネジメント能力の強化
組織の生産性と業績を向上させるためには、社員ひとりひとりのリーダーシップとマネジメント能力を高めることが不可欠です。
リーダーシップとマネジメントは、目標の設定と目標達成、メンバーとのコミュニケーション、問題解決と意思決定、顧客との信頼関係構築など、組織を運営するためになくてはならない核となるビジネススキルです。社員研修を通じて、社員のリーダーシップとマネジメント能力が向上することで、一体感のある強固な組織づくりが可能になります。
社員のモチベーションとエンゲージメントの向上
社員研修には、社員のキャリア成長をサポートし、従業員満足度やエンゲージメントを向上させる役割もあります。エンゲージメントが高まることで、社員は自分の仕事に対してこれまで以上の熱意と情熱を持ち、高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
企業理念の浸透とチームワークの強化
企業理念やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の浸透やチームワークの強化を通じて、組織全体の一体感を高めることも社員研修の重要な目的の一つです。企業理念やMVVは、社員が共有する組織の存在意義や指名、価値観や行動規範。また、チームワークとは、主体的に協力し合って目標を達成するための関係性やプロセスです。全社員が一緒になって同じ研修を受講する、共通言語や思考プロセス・判断基準を持つことは、協力関係や一体感を高めます。
結果として、社員研修を通じて 企業理念とチームワークが促進され、組織全体のパフォーマンス向上にも大きく寄与することになります。
組織における社員研修の重要性
現代の企業経営において、社員研修を通じた人材育成の重要性はますます高まっています。こうした背景も確認しましょう。
急速な技術革新
急速な技術革新に伴い、従業員の業務スキル・知識をアップデートすることが求められています。従業員のスキルや知識を最新のものにアップデートし、変化の激しい市場や環境に対応できる能力を育成するため、企業にとって社員研修は大切な取り組みの1つです。
優秀人材の流動化
人材の確保と定着は、どんな企業にとっても喫緊の課題です。優秀な人材であるほど、自分のキャリア構築への関心は高く、また転職にも困りません。社員研修を通じて、従業員のキャリア成長を支援することは優秀層のキャリア安全性ニーズを満たし、組織内で活躍し続けてもらうことが大切です。
社員研修を通じて、自分の強みや弱みを把握してキャリアビジョンや成長ビジョンを持ってもらう、また、成長実感を得てもらうことがエンゲージメント向上につながります。
社員研修は、従業員にキャリア自律の機会を提供し、企業内での活躍の場を広げることにも役立ちます。
組織文化とイノベーションの促進
VUCAの時代ともいわれ、WebやAI領域などを中心に業界と国境を越えた変化が起こる中で、企業を維持・成長させるためにはイノベーションが欠かせないものとなっています。しかし、確固たる歴史を持つ会社ほど、組織文化が硬直化し、イノベーションを生み出せないという課題に苦しんでいます。イノベーションを促進するためには、これまでにない創造的な思考や問題解決のスキルを社員が身につける必要があります。そのために役立つのも社員研修です。
イノベーションの創出方法やデザイン思考、アンコンシャスバイアスから解き放つ柔軟性などを身に付けることで、市場や顧客の変化を見ている現場社員の中から、事業やサービスの種となるイノベーションが生まれ、企業の将来の競争力を底上げされることが期待できます。
社員研修の種類
社員研修は知識やスキル習得に留まらず、組織全体のパフォーマンス向上や将来に向けたイノベーションの促進といった大きな恩恵をもたらしてくれるものです。しかし、社員研修といっても、実施の目的や形式、受講者の階層によって様々な種類があります。ここでは、以下に示した分類軸に基づいて代表的な社員研修の種類を簡単に紹介します。
・実施形式による分類
・研修プログラムによる分類
・階層による分類
実施形式による分類
大きな意味での研修の実施形式による分類として、以下の種類があります。
OFF-JT(Off-the-Job Training)
OFF-JTは職場外教育とも呼ばれ、社員が普段の業務から離れて行う教育訓練を指します。具体的には、セミナーや講義などの座学、各種のワークショップの他、オンラインでの学習プログラムなどが含まれます。OFF-JTは、体系だった理論・ノウハウ・知識を身に付ける、異なる視点やアイデアから新しい知見を得る、職場から離れた振り返りやリフレクション・課題設定を実施するといった目的で実施されます。
OJT(On-the-Job Training)
OJTは、実際の業務経験を通じて、個別具体的なスキル・知識、現場で求められる実践技術を体得することを目的に実施します。OJTは、業務経験の浅い新入社員が業務を行いながら、OJTトレーナーとなる上司や先輩からフィードバックを受けることで実践されます。なおOJTが、OJTという名の放置や現場実習になっていることも見受けられます。OJTの効果性を高めるためには、きちんとした事前設計やOJTトレーナーの技量が重要です。
OJD(On-the-Job Development)
OJDは、実務を通じて社員のキャリア開発や個人的成長を促進するための中長期的な社員育成を指します。実際の職場・業務を通じてという点は先述のOJTと共通しますが、OJTが新人を育成する限定的な期間のトレーニングを指すのに対して、OJDはより中長期的な視点で次世代リーダーや幹部育成していくための取り組みです。OJDには、新しいプロジェクトへの参加、ジョブローテーション、人事異動や配置等を伴う抜擢などが含まれます。
eラーニング
eラーニングは、パソコンやタブレットなどのIT機器を使い、動画やアプリを活用して学習する研修形式です。eラーニングは、Off-JTの一種ともいえますが、時間や場所に縛られず、本人のペースで学習可能な点が大きな特徴です。
eラーニングのメリットとして、
・実施費用を押さえやすい
・同じ品質・内容の研修を時間や場所を超えて提供できる
・オンライン上での受講管理が可能
などが挙げられます。
LMSと呼ばれる受講管理機能がついたeラーニングの管理システムを使うことで、研修担当者の管理負担を軽減できます。
研修プログラムによる分類
主にOff-JTにおける細かな研修プログラムによる分類として、以下の種類があります。
座学:
座学は、講師が一方的に情報を提供する形式による研修です。テキストやスライドを使ったレクチャーが座学の典型例で、受講者は基本的に講師の話を聴くことになります。座学は、体系だった理論や知識の習得、新しい概念や業界トレンドの他、会社方針などを効率的に学ぶ上で効果的な形式です。一方で、実務ノウハウを身に付ける、知識の定着率に課題があります。
個人ワーク:
個人ワークは、それぞれの受講者が単独で課題やワークに取り組む研修形式です。個人のスキル開発、業務へのブリッジング、業務の振り返り、内省などが扱われることで、座学の内容理解やブリッジング、自己理解が促進されます。一方で、個人ワークの効果は受講者のレベルに影響されるため、とくに未習熟者の場合には、個人ワークだけでは理解が深まりません。従って、個人ワークを思考時間としてグループワーク等と組み合わせると効果的です。
ペアワーク・グループワーク:
ペアワーク・グループワークは、受講者同士で2人もしくは何人かずつのグループに分かれ、共通の課題やテーマに取り組む研修形式です。ペアワークやグループワークは、ディスカッションや対話を通じて、個人の思考を深めたり、新たな視点に気づいたり、フィードバックをもらったりすることに役立ちます。また、コミュニケーションやチームビルディングの向上などを目的に実施されることもあります。集団内での役割分担やリーダーシップの発揮等の練習にもなるでしょう。
ロールプレイング:
ロールプレイングは、受講者がある特定の役割を演じながら、業務に関連した状況を模擬・再現する研修形式です。ロールプレイングは主に、顧客対応力や交渉技術、傾聴、コーチングなどのコミュニケーションスキルの習得に効果を発揮します。従って、販売や営業職、また、若手や管理職などのコミュニケーション研修で良く実施されます。実際に発生しうる業務状況を再現することで、実務とブリッジングされて状況に即した対応力が身に付く、また、実際に口に出して練習することで定着率が向上するといった点がロールプレイングのメリットです。
ケーススタディ:
ケーススタディは、実際のビジネスシナリオやある程度複雑な問題を模倣した事例(ケース)を用いて、受講者に具体的な状況分析や意思決定のプロセスを体験させるトレーニング方法です。ケーススタディは、受講者が学んだ理論を実際の状況に適用させることで、実務にブリッジングしたり、学習の定着率を上げたりする効果があります。とくにビジネススクールや専門性の高い研修プログラムで採用されており、複雑で簡単には正解にたどり着けないリアルな状況への対処法を身につける上で効果を発揮します。
対象階層による分類
組織が一定以上の規模になると、従業員は幾つかの階層に分かれることが一般的です。期待する成果や求められるスキルは、階層ごとに異なります。従って、社員研修を実施する場合も、階層別に行うことが多いでしょう。それぞれの階層に応じて実施される社員研修を解説します。
新入社員研修
新卒社員向けの研修は、社会人としての基本的な考え方やビジネスマナーを中心とした内容で実施することが一般的です。新入社員向けの主な研修としては以下があります。
●ビジネスマナー研修:
あいさつの仕方や身だしなみ、電話での受け答えなど、社会人としての基本的なマナーを学びます。
●ビジネススキル研修:
文書作成、仕事の進め方、ホウレンソウなど、社会人としてまず身につけるべきスキルを学びます。社会人として姿勢や心構えなども、ビジネススキルの一種と言えるでしょう。
●コミュニケーション研修:
相手の話に対する傾聴の仕方や、相手に伝わる表現方法など、仕事で成果をあげるうえで不可欠となる人間関係の構築に必要なノウハウを教わります。コミュニケーションは誰もが日常でやっている一方で、意外ときちんと教わる機会が少ないものです。きちんとした型を教えることが大切です。
若手社員研修
入社2年目以降の若手社員は、ある程度の基礎的なビジネススキルや知識は身に付けている一方で、専門性やリーダーシップ等については未熟です。また、入社数年目は仕事を覚えてくるからこそ、心の余裕が出来て、キャリア形成(キャリア安全性)への不安なども生じてくる時期です。若手社員向けの主な研修としては以下があります。
●ビジネススキル研修:
商談や販売などにおける実務的なコミュニケーションスキルなどを身に付けます。たとえば、営業職であれば、ラポール形成、ヒアリング、提案営業(ソリューション営業)、プレゼンテーション、クロージング技術、またKPIマネジメントやBANT判定など、各職種で必要となる専門的なビジネススキルを、1年目よりも細分化して深めます。
●リーダーシップ研修
リーダーシップは管理職にのみ求められるものではなく、すべてのビジネスパーソンに求められるものです。とくにサービスの高度化が進み、現場での対応力やイノベーションなどが重要になる中で、若手社員のうちからリーダーシップ育成を実施する企業が増えています。
●キャリア研修
上述のように入社2~5年目というのは、最初にキャリアに悩む時期です。多くの会社で、まだ「1人前」には至らず、大きな仕事を任せられる手前の状況です。一方で、ベンチャーやSNSにおいては既に管理職になる若手がいたり、華々しい仕事ぶりなどが取り上げられることもあり、焦りが生じます。ここまで成長を確認し、適切なキャリアビジョンを描き、仕事へのエンゲージメントを強めるキャリア研修が大切です。
中堅社員研修
中堅社員というのは会社によって年齢層が異なりますが、一般的には「20代終盤~30代でビジネスパーソンとしては既に1人前であり、管理職になる手前の層の社員」を指して使われることが多いでしょう。中堅社員には、後輩を育てたり、リーダーをサポートしたりしながら、マネジメント側に向かう準備が求められるようになります。そのため、中堅社員を対象にした研修は、マネジメントの基礎や課題解決力の強化などの実務的なスキルを身につける研修が多くなってきます。
中堅社員向けの研修では、主に以下があります。
●チームビルディング研修
チームにおける自らの役割を認識し、多彩なリーダーシップのスタイルを知ることで、個々の能力を最大限に引き出す大切さを学びます。
●課題解決、ロジカルシンキング研修
仕事で成果をあげる上で、人間関係の構築などはもちろん大切ですが、同時に、今後リーダー・管理職を目指す上では、課題解決やタスク管理、目標設定のスキルも求められます。その際に役立つのが課題解決やロジカルシンキングの能力です。
管理職研修
管理職は、組織運営の中心となる存在です。経営陣とメンバー間のパイプ役となり、リーダーシップを発揮して、チームや部門の成果をあげることが管理職には求められます。管理職を対象にした研修は、チームやメンバーを動かすためのヒューマンスキルや、実務を遂行するためのマネジメントスキルなどの習得を目的に実施されます。
管理職向けの研修では、主に以下があります。
●新任管理職研修
管理職に就任したばかりの人や、今後管理職として活躍を期待する人を対象に実施する研修です。管理職に求められる役割の認識や、目標達成のための業務マネジメントのやり方などについて学びます。
●リーダーシップ研修
リーダーシップは管理職だけに求められるものではありませんが、管理職には特に求められる素養です。リーダーシップ研修には、リーダーシップの考え方や効果的なリーダーシップスタイル、そしてリーダーシップを発揮するための実践方法などが含まれます。また、場合によっては自分のリーダーシップやマネジメントの現状を振り返り内省するような研修も実施されます。
●コミュニケーションスキル研修
メンバーのパフォーマンスを向上させたり、部下の成長を促進させたりするうえで役立つコミュニケーションスキルを身につけます。叱り方や褒め方、指示の出し方や報告の受け方、コーチングやファシリテーションなど、管理職特有のコミュニケーションスキルの習得を目的に実施されます。
●上級管理職研修
管理職経験を積んだ人を対象に実施する研修です。より高いレベルの意思決定や戦略立案、リスク管理、また組織マネジメントや変革のスキルや考え方を習得します。
幹部・役員研修
経営幹部や役員層は、事業の方向性を決定し、経営の舵取りを担う存在です。幹部や役員層には、事業をマネジメントをするうえで不可欠なマーケティング戦略やアカウンティングなどの知識も求められます。また、管理職よりも大きな組織をマネジメントする上では、ビジネスモデルやビジョンの構築につながるコンセプチュアルスキル、社員一人一人の心を動かすようなプレゼンテーション能力も必要です。さらに、組織に大きな影響を持つ意思決定をする立場だからこそ、コンプライアンスやリスクマネジメントに関しても一定の見識が必要となってくるでしょう。このように、事業責任者として大きな期待と責任を背負う幹部・役員層には、多岐に渡るスキル能力が求められます。
以下、幹部・役員向け研修として主なものを解説します。
●マーケティング研修
3C分析やSWOT、PESTなどの基本的な事業を捉えるフレームワーク、また、大きな視点で市場や顧客、ビジネスモデルを捉え、事業戦略につなげていくスキルです。
●コンセプチュアルスキル/プレゼンテーション研修
事業全体など、より大きな組織を運営する上では、ミッションやビジョンといった抽象的な企業理念、また、中長期視点での事業ゴールや事業計画などの構築・立案するスキルが必要です。マーケティングスキルと重なる部分もありますが、具体化されていない事柄を高い解像度で思考できる力を磨いていく必要があります。また、ミッションやビジョン、バリューの策定や浸透もコンセプチュアルスキルが必要となります。そして、これらを社員達に伝え、腹落ちさせるために、人を惹きつけるプレゼンテーション能力も高めていくことが求められるでしょう。
●アカウンティング研修
P/L(損益計算書)、B/S(貸借対照表)、CF(キャッシュフロー計算書)などの理解を含め、事業全体の運営、方向性や資源配分を決定する上で必須となるアカウンティング(企業会計)を身に付けます。
●コンプライアンス研修
不祥事防止や企業価値向上のため、コンプライアンス(法令遵守)の重要性や違反のリスク、遵守すべき法令や企業規則の知識を学びます。メンバー時代から学んでいる事柄ですが、意思決定する立場として、より深い理解が必要です。
●リスクマネジメント研修
企業が抱える様々なリスクに関する知識と認識を深め、トラブルの発生を未然に防ぐ手立てを習得します。
社員研修を実施するまでの流れ
ここまで社員研修の種類・分類を紹介しました。自社で社員研修を実施する場合、どのように進めていけばいいのでしょうか?ここでは、多くの研修で共通する企画から実施までの流れをステップ順に解説します。
研修の目的とゴールを明確にする
最初に必要なことは、研修の目的とゴールを明確にすることです。研修の目的とゴールが明確になることで、研修カリキュラムの内容や手法、評価基準なども決めやすくなります。
研修の目的:
研修を実施することで達成したい結果/解決したいテーマです。例えば、「営業チームの営業力を向上させる」「管理職がリーダーシップを発揮できるようになる」などです。
研修のゴール:
研修の目的を達成するために、具体的にどのような行動や成果を求めるかを定めたものを言います。例えば、研修の目的が「営業チームの営業力を向上させる」だとします。この場合のゴールとしては、「営業部全体で、クロージング成約率を20%向上させる」「今期のリピート率を50%以上にする」などになります。研修が終わった後に実現させたいこと、受講者の状態をなるべく具体的に描くと、その後のステップが実施しやすくなります。
研修の内容と方法を決める
前述のステップで、研修の目的とゴールを明確にできたら、次は研修の内容と方法を決めていきます。
研修の内容とは、研修で学ぶべき具体的な知識やスキルのことで、例えば、「新規営業における効果的なアプローチ方法」や「コミュニケーションの技法とコツ」などです。また、研修方法は、研修で用いる教材や手法、形式を選択することを言います。具体的には「社員研修の種類」のパートで紹介した、「ケーススタディ」や「ロールプレイング」「グループワーク」「講義」などがあります。実際には複数の手法を組み合わせて実施することが大半です。
研修の実施準備をする
研修の内容と方法が定まったら、研修を実施する準備を進めていきます。
研修の準備としては、日程や場所の決定、講師の手配、受講対象となる社員への告知、教材や設備の準備などが含まれます。準備を進める際は、研修の内容と方法に合わせて、必要なリソースや条件を確保することが重要です。研修効果を高める上では、受講者への告知、また場合によっては事前の面談などが大切です。
研修を実施する
研修の準備を整え、実施を迎えるに当たっては、以下の点に注意することが効果的です。
まず、研修の冒頭では、研修の目的とゴール、内容と方法、スケジュールや受講時のルールなどをしっかりに伝え、受講者の関心や参加意欲が高まるようにします。研修実施中は、質問やミニテストなどを随所で設け、受講者の反応を確認しながら進行を調整します。そして、研修終了後は、受講者から感想や評価、改善点などを聞くために、アンケートやレポートを提出してもらいましょう。アンケートやレポートが集まったら、なるべく早いタイミングで、研修の効果や改善点を確認することが大切です。
研修の振り返りとフォローアップ
研修は実施して終わりではありません。研修後に振り返りとフォローアップをすることで、研修内容の改善や次回の研修計画に活かすこと、そして、研修の効果性を高めることが大切です。
研修の振り返りでは、「研修の目的とゴールは達成されたか」「研修内容や方法は適切だったか」「受講者の満足度や理解度はどうだったか」「準備や進行に問題はなかったか」などについて確認しましょう。また受講者向けの研修後フォローアップでは、研修で学んだことを定着させるためのアクションが肝心です。受講者の上司やチームのマネージャーに協力してもらうようにしましょう。
「研修で学んだことを、現場で実践できる機会や環境を作ってもらう」「研修の学びを活用して成果を上げたメンバーに共有してもらう」といった取り組みが習慣になると、同じ研修をやっても研修効果はどんどん高まるでしょう。
ジェイックが提供する社員研修の強み
ここまで階層別研修の種類や、研修実施までの流れをお伝えしました。最後に企業向けに社員研修サービスを提供するジェイックの社員研修の特徴を3つ紹介します。
目に見えにくい「マインド・考え方」「ヒューマンスキル」の育成
研修において、業務の遂行に必要なスキルや能力の習得・向上することは重要ですが、それだけでは成果をあげるためには十分ではありません。知識やスキルを業務で活用して成果をあげるためには、社員自身の仕事に対する姿勢や価値観といった「マインド」や「考え方」が適切でなければなりません。しかし、マインドや考え方というものは、他者からは見えにくく、研修で教えるのも簡単ではありません。
ジェイックの社員研修は、こうした「マインド」や「考え方」を育成することに強みがあります。たとえば、ベストセラーとなった『7つの習慣』のフランクリン・コヴィー社と提携してリーダーシップ研修を提供します。『7つの習慣』の考え方は、ジェイックが提供する新入社員研修や管理職研修などのプログラムにも組み込まれています。これにより「主体性」や「自責の考え方」といった、自己成長と仕事の成果に欠かすことのできないマインドや考え方の醸成を実現します。
また、同じく目に見えにくいヒューマンスキルの育成も得意としています。名著『人を動かす』で有名なデール・カーネギー・アソシエーションと正式に契約し、管理職や次世代リーダー層向けのヒューマンスキル研修を提供するほか、ストレングス・ファインダー®の要素を組み込んだ強みを活かすコミュニケーションやマネジメントなどの研修にも強みがあります。

受講者の「行動変容」にこだわったカリキュラム
研修を実施する上で最も大切なことは、研修後の行動変容です。研修で学んだことを自分の業務につなげ、実際の仕事で活用して、具体的な成果が生まれて、はじめて研修は「成功」と言えます。しかし、研修を実施するだけでは、こうした行動変容はなかなか生まれません。
ジェイックの社員研修は、受講者の「行動変容」に強くこだわっており、研修内での業務とのブリッジングや実践行動を促進するためのワークや課題はもちろん、研修前後の働きかけや研修プログラム自体の設計にも行動変容を促す仕組みを強化しています。
たとえば、研修前には、受講者それぞれに現在の自分の課題や将来のありたい姿を明確にしてもらう、また興味付けにつながるワークや動画などを提供する。また、研修後には、研修内で作成した職場での実践計画を実行してもらい、フォローアップ研修で学んだことを業務でどう活用したのか?結果はどうだったのか?を振り返るプロセスを設けるといった形です。研修自体のカリキュラムも、学習⇒職場実践⇒振り返りを仕組みにした、タイムスペースラーニングと継続学習(Keep Learning)を取り入れるなど、研修だけでは終わらせず、その後の行動変容にコミットしています。

「受講者主役」の研修プログラムと進行
研修会社が取引先企業に社員研修を提案するにあたっては、取引先の意思決定者である経営者や経営幹部、人事のニーズにフォーカスしがちです。もちろん意思決定者のニーズに応えることは間違いではありません。しかし、社員研修における本当の主役は研修を受ける社員です。提案としてどんなに素晴らしく理にかなった研修プログラムであっても、研修を受ける社員達が自分事として関心を持ち、学んだことを業務で活用してみよう!と思えるものでない限り、研修の目的は達成できないでしょう。
そのため、ジェイックの研修は「受講者主役」という考え方を徹底しています。営業担当者と登壇講師が明確に役割分担して、講師は研修当日まで登場しない研修会社もありますが、ジェイックでは可能な限り、研修講師が提案・設計段階にも関わります。受講者のニーズやレベルに合わせて、研修の内容や進行方法をカスタマイズすることはもちろん、研修中も、受講者自身に課題や目標を設定させ、自ら考え、発言、行動してもらう。また、主体的に取り組んでもらえるよう、受講者に寄り添って承認しながら全力でサポートします。自らの学びと成長に主体的になり、研修後の実践に対しても高いモチベーションで取り組んでくれるようになるのが、ジェイックの「受講者主役」の研修プログラムです。

ジェイックの社員研修を受けた受講者の声
ジェイックの社員研修を受講した受講生の声の一部を紹介します。
- 「新入社員研修」受講生
講師の先生のまとめ方や要約がとても分かりやすく、今まで自分の言葉で表現できなかったことを腹落ちさせてくれる言葉に出会えてとてもスッキリしました。研修では、同期とディスカッションする時間があり、これからの仕事に取り組むうえでとても心強い機会になりました。
- 「営業研修」受講生
私は営業研修のロールプレイングでお客様役を演じたのですが、このことで自分の営業アプローチのヒントがつかめました。
- 「管理職研修」受講生
これまで他の研修を何度も受けたはずなのに、業務で活用できていなかったのが課題でした。しかし、今回の研修を受けたことで「しっている」→「している」にしていかなくてはと、意識が改まりました。
- 「管理職研修」受講生
部下に自主的に動いてもらうようにするには、その人の理解を深め、まず聴くことから始めることが大事なのだという気付きがありました。部下の長所をしっかり意識して聴き、コミュニケーションをよりよく改善していきます。
- 「若手研修」受講生
今の私が壁に突き当たっている原因として、自分の思考の癖が関係していることが分かりました。それが分かっただけでもためになりましたが、それ以上に不安が払しょくされ、今後の仕事にもモチベーション高く取り組める原動力になりました。
研修講師紹介
お申込みから研修までの流れ
お問い合わせ、資料請求
お問い合わせ・資料請求は、電話、Webフォーム、メール等で承ります。まずはお気軽にご連絡ください。
ヒアリング訪問
お問い合わせいただいたご担当の方へ、対面もしくはお電話で、お問い合わせいただいた背景や目的などをお伺いいたします。その上で、貴社のご要望や課題に沿った研修コンテンツを作成いたします。
コンテンツ作成、企画書の提案
ヒヤリング内容を基に、弊社で企画書を作成いたします。企画書は、現状の課題、企画の目的(ゴール)、スケジュール、コンテンツ内容、講師、見積費用などを含んだ内容で提出いたします。
ご契約
企画書の内容でご納得いただき、実施日(会場)、講師が確定しましたら、ご契約の手続きに進みます。申込書の受領を持って契約完了となります。
研修実施
企画書の内容を骨子に、実施前までに講師と打ち合わせを行い、研修を実施いたします。
社員研修に関してよくある質問と回答
研修の効果はどのように測定しますか?
研修の効果測定は、例えば、研修前後のテストやアンケート、業務の成果や評価、上司や同僚のフィードバックなどがあります。研修の効果を測定することで、研修の改善やフォローアップに活かすことができます。
研修前に、参加者のモチベーションを高めるにはどうすれば良いですか?
研修前に参加者のモチベーションを高めるには、以下のような取り組みを実施すると効果的です。
・研修の目的と、参加者が得られる具体的なメリットを明確に説明する
・研修後にどのようなスキルや知識が身につくかを具体的に示す
・事前アンケートなどを通じて、参加者の期待や課題を把握する
・個別に上司から期待事項や成長テーマなどを伝える面談を実施する
・可能な範囲で、個々の参加者のニーズに合わせてプログラムをカスタマイズする
弊社の課題やニーズに沿った研修カリキュラムにしていただくことは可能ですか?
はい、可能です。ジェイックでは、お客様の課題やニーズをヒアリングした上でカスタマイズした研修カリキュラムをご提案します。研修内容や方法、期間や回数など、要望に応じて柔軟に対応可能です。
実際の研修で使用している動画や内容を見せていただくことは可能ですか?
はい、お問い合わせいただけましたら、個別に担当より投影資料の一部等をお見せすることは可能でございます。フォームよりお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝除く)